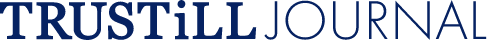議決権は渡したくないけど増資はしたい?株主に与える権利を調整できる、種類株式の基本
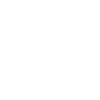

皆さん、「優先株式」「優先株」という言葉を聞いたことのある人も多いのではないでしょうか。ところで、この「優先」とは、何に対して、なのでしょうか。
ここでは、優先株式を含む種類株式(会社が発行する、2種類以上の株式)の基本的な仕組みやどのような特徴があるのかご説明します。
そもそも株式とは?
株式とは、企業が資金を集めるために発行する証券のことで、大きく分けて2つの権利からなります。
①議決権
会社の株主総会で議決権を行使できる権利(議決権の行使を通して会社の経営に参画する)
②配当を受ける権利
会社が利益をあげたときに、その中から配当を受ける権利

原則、株式は平等な扱い
先ほどご紹介した①議決権、②配当を受ける権利は株式の保有数に応じて平等に与えられます。株主は誰でも平等に扱われることが原則とされています。
①議決権 ⇒ 保有する株式1株につき1個
②配当を受ける権利 ⇒ 株式1株あたり同じ(例:株式1株につき10円ずつなど)
ただし、企業が発行する株式には種類があり、議決権や配当に関して「原則」以外の特別な取り決めがされているものがあります。それが今回ご説明する「種類株式」です。
種類株式とは?~株式の種類ごとに扱いを別にできる~
定款で定めることにより①議決権、②配当を受ける権利について異なる扱いをする2種類以上の株式を発行することができます。これを「種類株式」といいます。
種類株式の例として、①議決権、②配当を受ける権利の取り扱いについて次のような差をつけることができます。
例:
①議決権
- 普通の株式は株式1個につき議決権1、他の株式は議決権なし
- 取締役の選任は、普通の株式にのみ議決権を行使できる(他の株式は、取締役の選任議題で議決権を行使できない)
②配当を受ける権利
- 1株当たりの配当について、他の種類の株式は、普通の株式よりも10円多くする
- 他の種類の株式に先に配当し、配当原資が残っていたらその範囲内で普通の株式に配当する
このように、種類株式は株主に与える権利が普通の株式とは異なる特徴があります。株式の取り扱いを変えることで、株主に与える権利を調整し、さまざまな目的に対応することができます。

例えばこんな場合に…「優先株式」
種類株式の一種である「優先株式」は、配当は普通の株式よりも多めにする代わりに、株主総会で議決権を行使できない、としていることが多いです。
会社の創業をした方の中には、株式を発行して増資をし、資本金を増やしたり投資をして会社を大きくしたい、と思うことがあります。しかし、株式を発行すると、①の議決権も出資者に渡すことになり、会社の経営権が創業者から離れてしまったり、そこまででなくても創業者だけで会社経営を行えなくなる、ということになってしまいます。
そこで、増資はしても議決権は今までどおり創業者が独占したい、と考える場合に、種類株式の出番となります。
出資と引き換えに、「優先株式」(つまり①の議決権は行使できないけど②の配当を受ける権利は多めにする、という種類株式)を発行して増資を行い資本金は増やすけれど、会社の議決権は普通の株式を全部持っている創業者が今までどおり100%保有する、という対応をします。
この場合、出資をする人は、議決権を行使できなくてもいいのか、と疑問に思うかもしれません。しかし、配当を重視したり、会社経営は創業者にお任せでいい、という人はよくいます。そのような方々からすると、「優先株式」の方がいい、となるわけです。
他にもこんな種類株式があります
拒否権付き種類株式(「黄金株式」)
全ての事項か、所定の一部の事項(例えば取締役の選任など)は、ある種類の株式を有する種類株主総会の決議を必須とする、という種類株式です。
全体の株主総会等で決議された事項でも、この種類の株式を有する株主は覆せる、ということで拒否権付き種類株式といい、「黄金株式」ともいいます。
例えば、創業者のみがこの種類株式を有することで、その意向に沿わない決定ができなくなりますので、強力な武器になります。(ただし、全体の株主総会等で否決された議案を復活させることまではできない点に注意が必要です)
取得条項付き株式
株主総会の特別決議により、またはある一定の事由が生じた場合に、会社が、その種類株式を株主から取得する、と定められた種類株式です。
一定期間だけ増資をしたいが、それが終わったら元に戻したい、という場合に有効ですが、株主からこの種類株式を取得するときは、金銭や他の株式を代わりに交付するのが一般的で、かつ定款に定めます。そのときの対価まで見据えて検討する必要があります。
種類株式は何でもあり、というわけではない
種類株式は、どのように定めてもいいわけではありません。
例えば、議決権がないと定められた株式でも、会社経営に関する大変に重要な議題によっては、議決権を行使できると会社法で定められています。完全に無議決権にはできません。
導入の際は、どのような内容の株式にしたいか、その内容の設定が会社経営や税務の面で裏目に出る場合がないか十分検討されることをお勧めします。
種類株式を導入するときの注意
種類株式の発行には、定款で、株式の内容(議決権をどうするか、配当をどうするかなど)を具体的に盛り込まなければなりません。一般に、種類株式に関する規定は、ボリュームが大変多めで、作成の難易度が非常に高いものです。
また、株主総会は、全体の株主総会以外に株式の種類ごとの総会(種類株主総会)の開催が原則必要になるため、会社の機関の設計に関する定款の規定も大幅な見直しが必要です。
導入のために、定款を改正しますので、必ず株主総会を開催して、特別決議による決議が必要です。
決議後は、法務局へ、種類株式の内容など所定の事項の登記を申請することになります。
種類株式の導入は、先述のとおり、難易度が非常に高く、また定款の規定次第で、導入後の影響が大きくなります。さらに、税務上の導入により不利にならないか、税務面の検討も必要です。
専門家と相談しながら進められることをお勧めします。
 このサイトについて
このサイトについて