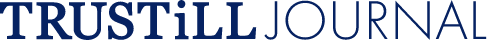貸金業を始めるには?
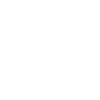

貸金業というと、駅前などでよく見かける消費者金融をイメージする方も多いと思いますが、実際には、信販会社やクレジット会社、リース会社など多くの業態の事業者が貸金業登録をし、金銭の貸付けを行っています。また、貸付けをしなくとも、借り手と貸し手の間に立って契約の締結・勧誘を目的とした商品説明等を行う際も貸金業登録が必要です。
近年、貸金業登録を希望される方が増えていますが、「他の許認可よりもハードルが高そう」「何から手をつけていいのかイメージができない」というような声も多く聞かれます。
今回は、貸金業登録の準備としてどのようなことを行わなければならないのかご説明します。
①登録要件を満たしていることの確認
登録申請に関する書類を一式準備しても、肝心の要件を満たしていなければ登録は受けられません。まずは法令で定められた以下の登録要件を満たしているかについて確認をしていただくことが必要です。
登録要件
- 営業所又は事務所ごとに、貸金業務取扱主任者を設置していること
登録申請者が法人である場合は、常勤の取締役又は従業員の中から、貸金業取扱主任者を選任する必要があります。貸金業取扱主任者に選任された者は常勤である他に、兼業・兼任はできません。また、貸金業取扱主任者資格を有しているだけでは条件を満たしませんので、日本貸金業協会で登録をする必要があります。有効期限も3年と限られておりますのでご注意ください。 - 財産的基礎を有していること
純資産額が5,000万円以上であることが必要です。
登録申請時に直近の貸借対照表を提出し、財産的基礎を有していることを証明しますが、決算時に満たしていなくとも、その後の増資により5,000万以上となった場合にはその増資にかかる登記書類等の追加書類が必要になります。 - 貸金業を的確に遂行するために必要な体制が整備されていること
(1)定款又は寄付行為の内容が法令に適合していること。
具体的には定款又は寄付行為の写しを提出し、その目的欄に『貸金業(推奨)、金銭の貸付け、融資』のいずれかが入っていることが必要となります。(2)常務に従事する役員のうち、貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいること。
(3)貸付けの業務に1年以上従事した経験を有する者が営業所又は事務所ごとに1名以上いること。
※(2)と(3)は兼務が可能です。(4)貸金業の業務に関する社内規則・組織図を定めていること。
なお、上記の他に、都道府県によっては独自の審査基準を設けている場合があります。
ここでは東京都の基準を紹介します。
営業所又は事務所を設置し、固定電話を設置していること
(1)審査の際に現地調査が行われ、営業所又は事務所が実在するかについての確認と、当該電話番号に誤りがないかを確認するためその場で電話をし、調査します。
(2)親会社等のグループ会社と同居している等、同一フロアに他法人と同居している場合は扉やパーテーション等で区切る必要があります。なお、パーテーション等で区切る場合は、申請前に東京都に相談をしておくのが望ましいでしょう。
(3)営業所が賃貸物件である場合は、賃貸人(転貸借の場合は、転貸人と所有者)が当該営業所において貸金業を営むことを了承している旨が記載された書面(承諾書等)が必要となります。
なお、申請時に賃貸借契約書の写し(転貸借の場合は、転貸借契約書に加えて、転貸人と所有者間で締結された賃貸借契約書も必要です)を提出しますが、賃貸借(転貸借)の契約期間は2年以上であることが必要となります。
※営業所がレンタルオフィスの場合は、事前相談が必要な場合がありますので注意が必要です。
②必要書類の準備
上述した登録要件を満たしていることが確認出来次第、必要書類の準備に入ります。
必要書類は主に以下のとおりです。
- 登録申請書
- 役員、貸金業取扱主任者等の履歴書や証明書類等
- 営業所の案内図、フロア図面
- 貸借対照表
- 貸金業に関する社内規程 等
この中でも、最も作成に時間を要するものが貸金業に関する社内規程です。
『貸金業者向けの総合的な監督指針』において「II.貸金業者の監督に当たっての評価項目」の各項目の主な着眼点に加えて、貸金業協会の自主規制規則の水準に則った適切な社内規則等の作成が求められているため、法令等を確認しながら社内規程を作成する必要があります。
①②が揃って初めて登録申請が行えるようになりますが、
その後も現地調査や都道府県によっては面談があり、提出書類の補正が発生する等、申請後も登録が完了するまで対応すべきことが多くあるため、ご自身で申請をするのはハードルが高いと思われるかもしれません。適切かつ円滑に進めるために専門家に相談するのもよいでしょう。
 このサイトについて
このサイトについて