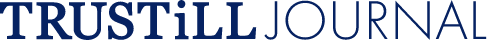宅地建物取引業免許とは
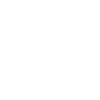

いわゆる『宅建業』ですが、具体例としては、駅前などでよく見かける不動産屋をイメージしていただけるとわかりやすいのではないでしょうか。
不動産屋は、規模の大小に関わらず、宅地建物取引業免許を持っていないと営業できません。
ここで注意していただきたいのは、自己所有のマンション等を他人に賃貸する場合には、免許がなくてもできるということです。逆を言えば、これ以外の不動産の取引を業として行うためには、宅建業が必要となります。
また、上述したような不動産屋以外でも、宅地建物取引業免許が必要となるケースとして不動産ファイナンス関係の会社が挙げられます。
ファイナンスに強い当グループでは、このような一般の仲介等を行うわけではない会社様からの宅建業免許取得のご依頼もスムーズに対応させていただくことが可能です。
免許の区分
宅地建物取引業免許には2種類あります。
①大臣免許
2つ以上の都道府県にわたって営業所を設置する業者が申請する免許で、国土交通大臣に申請を行います。
②知事免許
1つの都道府県に営業所を設置する業者が申請する免許で、各都道府県知事に申請を行います。
免許の有効期限
免許の有効期限は5年です。有効期間後も引き続き営業を続ける場合は、有効期間の満了する90日前~30日前までに更新手続きを行う必要があります。
必要な要件
①専任の宅地建物取引士の設置
営業を行う事務所ごとに、専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。
『専任』というワードからも連想できるように、『専任性』及び『常勤性』が求められますので他業務との兼任や、他法人との兼業はできませんのでご注意ください。
この専任の取引士の設置人数については、宅建業務に従事する従業員5名につき1名設置する必要がありますので、従事する従業員と専任の取引士の人数管理には日頃から注意が必要です。
②事務所の設置
事務所の形態について、一般的な解釈としては、物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能をもち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要となります。
このため、一般の戸建て住宅やマンション等の集合住宅を事務所として使用する場合は状況により免許がおりない場合も十分にありますので、平面図等を用意して、事前相談をすることをおすすめします。
③欠格事由に該当しないこと
暴力団の構成員である、免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合、心身の故障により宅地建物取引業を適正に行うことができない場合等、宅地建物取引業法第5条に定められた欠格事由に1つでも該当する場合は、免許の申請をしたとしても拒否されることになりますので、確認が必要です。
業務開始までの期間
免許がおりてからすぐに営業を始めることができると思われる方もいますが業務開始までのスケジュールについては、以下が目安になります。
| 宅建業登録申請 | ||
|---|---|---|
| ↓ | 標準処理期間は、知事免許の場合は30~40日、大臣免許は100日です。 ただし、審査中の補正期間は上記期間に含まれません。 |
|
| 免許 | ||
| ↓ | 普通ハガキにて本店住所へ送付されます。 | |
| 営業保証金の供託 ↓ 供託の届出 |
or | 保証協会への加入 |
| ↓ | ||
| 免許証交付・営業開始 |
『営業保証金の供託』と『保証協会への加入』のどちらかを選ぶかにより営業開始までの期間は大きく異なってきます。
供託については、1営業所あたり500万円を管轄法務局に供託し、それを届出さえすればすぐに免許証の交付を受け、すぐに営業開始が可能であるのに対し、保証協会への加入の場合は、加入までの期間が1~2か月必要となります。
 このサイトについて
このサイトについて